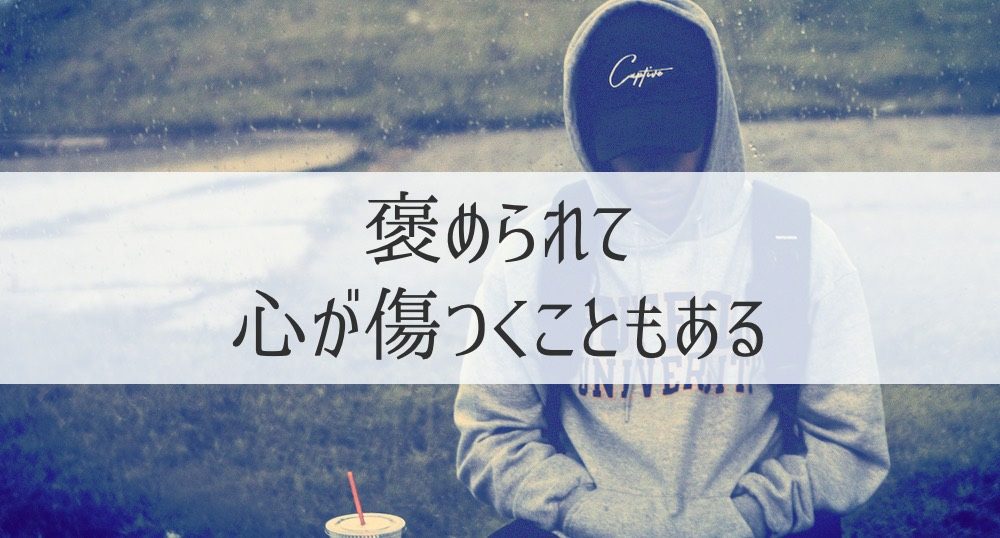「子供は褒めることが大事」
「ほめ育てが子供の自尊心を育てる」
「コンプリメントで自信の水を注いであげよう」
子供の褒め方に関しては教育学や心理学の観点からさまざまなことが言われています。もちろん、「褒めることは大事」という基本スタンスはどれも同じ。
しかし、とにかく褒めりゃいいってもんでもありません。やってはいけない、逆効果な褒め方もあるのです。
この記事ではだめな褒め方を3つご紹介したあと、なぜそれがだめなのか、効果的な褒め方のポイントはどこなのかを、元塾講師の経験を元にお伝えします。
やってはいけない子供の褒め方3例

子供は褒めてあげるのが大切。これは事実。しかし、逆効果になる褒め方もあるんです。とりわけ中学生ともなると少々気をつけねばならないポイントもあるので、具体例を交えつつご紹介しましょう。
「先生、私のことバカにしてるん?」
学習塾講師になってから、私はなるべく小さなことでも生徒を褒めるようにしていました。この基本方針はよかったらしく、特に小学生などは「もっと褒めてー!」といつも喜んでくれていました。
そんなある日、自習スペースで数学をやっていた中学生に質問を受けたので、一次方程式の解き方について解説をしました。で、確認のため基礎的な問題を紙に書いてやらせてみたらすぐ解けましたので、私はいつものように、
「すごいな、〇〇さん。ちゃんとできるやんか!」
と褒めました。
しかし、彼女は固まったように動かない。嬉しそうなそぶりはありません。
(あれ、どうしたんだろう?)
すると、彼女は言いました。
「先生、私のことバカにしてるん?」
私はすぐに、「しまった」と思いました。褒めようという意識が先行しすぎて、その子にできて当たり前のことまでうっかり褒めてしまったのです。「バカにされた」と受け止められて当然です。
これは塾講師をやっていたとき、「褒め」に関して犯した最大の失敗でした。
「すごいじゃん! 次は90点以上も狙えるね」
今度は、自分が子供の頃のエピソードです。
中学生のとき、苦手だった国語で80点を取ったことがありました。理科や数学は得意でしたが、国語はとりわけ嫌いだったので、自分からすれば80点はかなりいい点数です。
だから、親から褒めてもらえると思って期待していたのですが、このように言われました。
「国語が80点、すごいね。次は得意な数学とか理科みたいに、90点以上も狙えるかもよ」
これを聞いた私は、なんだかゲンナリしました。
表面上は「すごいね」と褒められています。しかし、他の得意教科と比べられ、「次は」とさらなる要求を出されたことで、複雑な気持ちになったのです。
当時はうまく言語化できていませんでしたが、大人になったいま整理してみるとこういうことです。
「理科や数学は得意だから90点取れる。でも、国語は苦手で、すごくがんばった結果の80点だ。なのに、同じように比べられても困る。しかも、なんですぐに『次』を期待するんだよ」
次は90点以上などと、即座により高い目標を言われると、すごくがっかりします。それは、親が無意識に減点方式で考えているから。それが子供だった自分にも伝わったから。
この場合でいうと、親には「国語でも90点以上取って欲しい」という暗黙の期待があって、80点は「そこからマイナス10点」という捉え方をしてしまっている。これが言葉と態度から伝わってしまうのです。
「これはきみが努力した結果だよ」
これも、わたし自身の中学時代のエピソードです。
あるとき、社会のミニテストでかなりいい点数を取れたことがありました。30点満点中の28点とか、そんな感じだったと思います。社会が苦手だった私にとってはかなり好成績です(文系科目は苦手だし嫌いだったのです)。
このとき、社会科の担当であり、担任でもあったH先生はこう言いました。
「よくがんばったね。これは清水が努力した結果だよ」
でも、実は違いました。そのとき、私はたいした努力をしていなかったのです。本当に、たまたま得意な部分が出題されただけで、どう考えてもラッキーパンチの28点だったのです。
なので、私は連絡帳にこう書きました。
「社会のミニテストは勉強してないのにいい点数が取れました。努力したからではなくて、まぐれで取れました」
ちょっと反抗期っぽい、中二病的な内容です(実際に中二だったのでお許しください)。
で、あとで返ってきた担任からの返事はこんなもの。
「日頃の努力が報われたんだよ」
つまり、担任としてはあくまで「努力の成果だ」で押し通したわけです。
そのように言いたい気持ちもわかります。が、しかし、当時の私としては「ラッキーで点数が取れることもあるんだ」と言いたかったのです。「テストってそういう面もあるでしょ?」と。
それを「努力の結果だ」の一辺倒で来られると、「こっちの話を聞いてない」「否定された」という気分になってしまいます。
ちょっと伝わりにくい話だったかもしれませんが、これにより、私の中でその担任教師に対する信頼感は著しく損なわれました。
心に響く褒め方には「承認」が不可欠

以上、3つの例にはある共通の失敗があるのですが、何だと思われますか? 褒めているのにだめだった、その要因は何でしょう?
それは、「相手のことをよく見ていない、考えていない」ということだと思います。
「すごいじゃん、よくできたね」と私が生徒を褒めたとき、相手はどう受け取ったか。きっと、「私のレベルをわかってないんだな。バカだと思ってるんだな」と感じたことでしょう。
国語で80点を取ったのにさらなる要求をほのめかした私の親は、私のことより自分の願望(90点以上取って欲しい)に心が向いていたし、担任の社会科教師は、連絡帳に書いた私のメッセージを汲み取れていませんでした。
つまり、だめな褒め方には「承認」が感じられないのです。よく見ているからこその褒め方になっていない、いわば、だれでもできる褒め方でしかないのです。
これに気づいたのは、いまYouTubeで人気の講演家・鴨頭嘉人(かもがしら よしひと)さんの動画を見たときでした。
要約するならこういうことです。
褒めるにしても、叱るにしても、土台には「承認」が必要。つまり、日頃からどれだけその人のことを「見ているか」が大事なんだ。これがなければ何を言っても心に響かない。
図にするとこうです。

「なるほど」と、完全に腑に落ちました。
世の中には褒め方に関してさまざまなノウハウがあります。
- すぐに褒める
- 具体的に褒める
- 成果ではなく努力を褒める
- 感謝のことばを伝えて褒める
どれも大切なことには違いありませんが、いちばん大事なのはこの「承認」です。「承認」がなければ、これらのノウハウ通りに褒めたところで相手の心に届きません。相手が中学生ともなれば「上っ面の褒め方をしやがって」と見透かされてしまうでしょう。
逆に言うと、日頃から相手を見ていて、その人のことを「思っている」と伝われば、下手クソな褒め方でも伝わるはずなのです。
まとめ
私の経験を踏まえ、やってはいけないNGな褒め方をご紹介しました。
それらに共通するのは「承認」がないこと、「ちゃんと見ている」と伝わらないことでした。一方、「承認」があればどんな褒め方でも伝わるはずです。
もしお子さんを褒めるのが苦手なら、まずはいいところを10個、紙に書き出してみましょう。日頃からしっかり見れていれば、出てくるはずです。もし詰まるようなら、もっとお子さんのことをよく見てあげること。
そうすれば、ノウハウなどなくたって「褒め」の達人になれるでしょう。
IT教材すらら、評判通りのクオリティなのか1ヶ月使ってみた検証結果【画像多め】
(通信教材「すらら」なら、管理画面から子供の学習状況が丸わかりで褒めやすく、おすすめです)