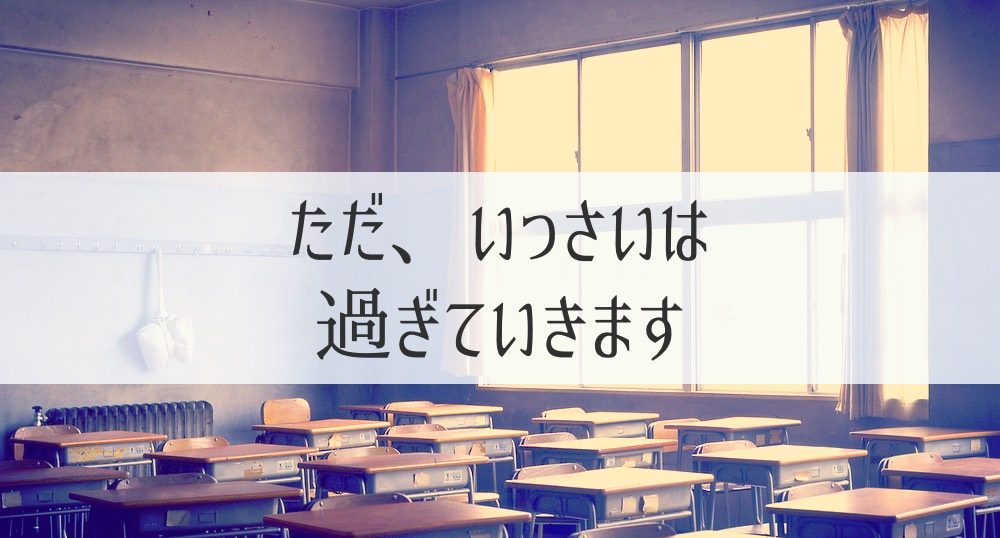「これはいったい、何をやっているんだ? 先生がしゃべっているのは異次元の言葉か? ここはどこ、私はだれ?」
これは高校3年生のときの私の心理です。ええもう、授業中は何がなんだかわからず、異世界へ放り込まれたような感覚でした。
中学まで優等生だった少年がいかにして落ちこぼれていったか、その経緯を1年生から3年生まで、順を追って回想していきましょう。
目次
1年生:人生で初めて勉強につまづく

私は、中学までは定期テストで平均80〜90点を取る、典型的な優等生でした。田舎で子供の数が少ないこともあり、学年1位を取ったこともあります。
しかし、進学校と言われる高校へ入ってみると、それまで通りにはいきませんでした。割と早い段階で勉強につまづくことになります。
数学の補習授業で洗礼を食らう
1年生の通常の授業は一応ついていけたものの、私は放課後にあった数学の補習授業で「洗礼」を受けることになりました。
それは副担任でもあった数学の教師が自主的に行っていた、希望者向けの補習授業で、センター試験や大学入試の問題に取り組むというもの。ふつうの授業中は扱わない高度な問題がバンバン出てきました。
つまり、熱意ある先生が「わが校の進学実績」をあげるべく、入学間もないうちから叩き上げてやろうという趣旨の勉強会です。
そこで私は、はじめて得意な数学で「わからない」感覚を味わいました。
それまでは、たとえ解けなかったにしても解説を聞けば次からはやれて当然だったのですが、そのときのは無理。解説を聞いたとて、「自分じゃ解けないわ」となってしまった。
今思えば、さすがに公立高校1年生で大学入試の過去問なんて難しくて当然なんですが、たぶん、このときが「勉強につまづく」という最初の経験でした。
暗記中心の勉強がイヤになる
暗記ばかりの勉強に嫌気がさしてきたのも、高校1年生のとき。
「高校に入ったら、中学までとは全然違うぞ」
こんなことを中学時代に聞いていて、それを真に受けていましたので、私は高校という教育機関にもっと高度でクリエイティブですごそうなイメージを持っていました。一般人がハーバード大学とかケンブリッジ大学に抱くような幻想を持っていたのです(たかが田舎の進学校に)。
しかし、いざ高校に入ってみたら中学の延長でしかない。
40人が教室に集まって、英数国理社と別れた科目をそれぞれの先生が板書しつつ教えるだけ。目標が、高校受験から大学受験に変わったにすぎません。
しかも勉強のメインは暗記で、英語なら単語やイディオム、数学なら公式や解法、化学なら元素記号など、覚えてばかり。思考力も必要ではあるけど、結局は受験対策にすぎません。
「これじゃ中学と同じじゃないか」
失望した私は、そんな勉強にははやくも嫌気がさし、成績はクラスの真ん中、あるいはそれよりちょっと下という微妙なポジションに落ち着きました。
2年生:不登校気味で授業がわからなくなる

2年生になると、私の不登校傾向がむくむくと頭をもたげてきました。1年次の遅刻・欠席はごくわずかでしたが、2年生に上がるとぽつぽつ休むようになり、中盤から後半にかけて尻上がりに不登校が急加速。
知識が虫食い状態となるため、授業がますますわからくなっていったのです。
数学ってどこまであるの?
もともと得意だった数学。1年生では数学1とAをやりましたが、2年生になる少し前から数学2・Bに入ります。ここでちょっとした疑問を抱きました。
数学って、どこまであんの?
数学2・Bがあるってことは、数学3・Cもあって、下手したら数学4・Dとか数学5・Eもあるのかも。いったいどこまでやればいいんだ?
もちろん、そんなのは少し調べればわかる話なんですが、当時は勉強自体に嫌気がさし、まともに知ろうともしなかった。で、漠然と恐怖感を抱いていました。高校の勉強の全体図、マップが描けていませんでした。
内容的にも、数学Bではベクトルというわけのわからないものが出てきます。数学のくせになんか物理っぽくて気に食わない。やる気にならない。
あとで考えると、高校2年生のときは大学受験のシステムを知らないため、逆算ができないのが苦痛でした。私立なら3教科でいいとかも知らない。ただ、目の前に謎の科目・単元が次々出現してくるばかりで、終わりが見えないのです。
となると当然、やる気はますます低下。学校自体が嫌になってくるのでした。
中学のときの貯金でしのぐ
勉強はきらいになってるし、遅刻・欠席が増えるからますます授業がわからない。けど、まだ定期テストでは中の下か、下の上くらいはキープしていました。
それはひとえに、中学時代の貯金があったからです。
英語や社会科系は、中学と高校とで本質的なちがいはありませんから、何とか過去の遺産でやりくりできる。赤点ぐらいは回避できました。物理にしても、よくわからないけど、数学の比を使って別角度から解くことで部分点を稼ぎ、40点くらいは取ることができていました。
それから、欠席がちとは言え、まだ完全には落ちこぼれたくないという意志がありました。なので、虫食い状態の出席でもいくらかは頭に入っていたようです。
2学期3学期とだんだん成績は下がっていましたが、それでも私はまだ「成績の芳しくない生徒」ぐらいのポジションはキープしていたのです。2年生のあいだは。
3年生:授業がまったくわからなくなる

2年生の後半、私は担任と親に「高校を中退したい」と切り出しました。散々迷った末に。ですが、これは認められず、私は不本意ながら在学し続けることになりました。
しかし、内心ではもう高校を離れたいと思っていた。その決意をした。と、その状態で無理に通わされたって、真剣に学業に取り組めるはずはありません。
授業をわかろうとする気もない
3年生の頃の私は無力感をベースとし、もう何がどうなってもいいという心理状態でした。週に1日2日は欠席で、登校したとしてもかならず遅刻。
こうなると「授業がわからない」というより、わかろうという気もない。ただ学校に顔を出すというだけです。
化学はたしか、有機化学という分野に入ったのですが、まず「有機」が何かわからない。無機化学というがあったらしいぞ、というぼんやりした知識はありましたが、違いはわかりません。中学でやった元素記号とかもだいたい忘れていました。
「これはいったい、何をやっているんだ? 先生がしゃべっているのは異次元の言葉か? ここはどこ、私はだれ?」
自分がそこにいることに現実感がなく、だれともコミュニケーションがないから自己認識も覚束なくて、当時はぼんやりした夢の中にいたような感じでした。
物理もちんぷんかんぷん、古文は呪文にしか聞こえない、数学3Cでは行列とか立体の積分が出てきましたが、数学2Bができてないからほぼ解けません。ひどいときには数学で100点満点中の3点を叩き出すまでに落ちぶれました。
でも、ここで意外な事実をお伝えしましょう。その頃の私には、危機感や焦りはまったくなかったのです。
「ああ、先生が何か言ってるな。おや、中庭の木に鳥がとまってる」
もう授業をわかろうという気もないので、諦めの境地に達していたのです。記憶がぼんやりしていますが、3年生のときの授業中は、1、2年のときより穏やかな気持ちで席に座っていたような気がします。
ただ、いっさいは過ぎていきます。自分が今まで阿鼻叫喚で生きてきた、いわゆる人間の世界において、たった一つ、真理らしく思われたのは、それだけでした
太宰治『人間失格』の末尾に書かれている、まさにあの心境です。
新品同様の英文法テキスト
受験でもっとも大切な英語はどうだったかというと、これも壊滅状態。3年生からはたしか「構文」とか「英文法」に授業がわかれたのですが、その違いもわかりません。
「英文法」の担当は、当時60歳くらいの教育熱心なF先生でした。1学期の始業式で、
「5組の副担任はF先生です」
と発表されるや否や、5組から悲鳴が「キャー!!」と湧き起こるような厳しい先生です。
ある日、私のクラスでの授業中、F先生は教室中を見回し、
「この英文法のテキスト、これを見ればみなさんがどれくらい勉強してるか一目瞭然ですよー」
なんて言い出した。
それは1年生のときに配布された分厚いテキストだったのですが、先生が机のあいだをまわりながら生徒たちのを一つひとつ見て、汚れ具合をチェックしていきました。ある生徒のは手垢で黒くなっており、また別の生徒のは使い込んで厚さが1.5倍くらいになっている。
で、私のところまで来て、見ると、先生はこう言いました。
「これは……2冊目?」
そう思うのも無理はありません。私のテキストには汚れひとつなかったのですから。厳しいはずのF先生もただ唖然とするばかり。
すでに2年は所有してるのに、書き込みもなければ折って広げた形跡もない新品同様のピカピカな状態。そのまま新入生に渡してもきっと違和感ゼロ。Amazonで「ほぼ新品」で出品できる保存状態でした。
それくらい、勉強はしていませんでした。
中間テストでほぼ最下位に
2年生までは、定期テストで40人中の30位くらいだったように記憶しています。しかし、3年生になるとさらに成績は下降していきました。
2学期の中間テストは壊滅的な出来で、自分の感触としてはクラス最下位確定。これ以上低い点数を取るのは難しいというレベル。
実際にどうだったかというと、たしか40人中の38位とか、それくらいでした。ひどいものです。
ただし、38位ということは下に39位と40位、二人いるということ。これは私にとってかなり衝撃でした。この中に、私よりひどいやつが二人もいるのか、と。
自己認識としては、自分はクラスのどのグループにも入れない、遅刻・欠席ばかりの圧倒的劣等生。しかし、他のメンバーの中に、自分より勉強のできない人がいる。これは一つの発見でした。
それから模試や実力テストはどうだったかというと、これも英語や理系科目は壊滅。まともな偏差値はつきません。が、たった一つ、人並み以上の成績がつく科目がありました。それが現代文。
当時、だれとも話さず本ばかり読んでいたため、読解力と語彙力だけは格段に上がっていたようで、現代文だけ偏差値70以上、学年で3位を取りました。読書の力は偉大です。
「おまえら、理系教科はいいけど文系がひどいな。何とかしろよ」
担任は一人ひとりの成績のレーダーチャートを見ながら結果を返却していましたが、私のになるとギョっとして言いました。
「清水、おまえだけチャートの形が逆だぞ!」
見ると、私のチャートは面積の少ない、国語だけ尖った針みたいになっていました。
その後も成績が改善することはなく、朝のホームルームに出ないから受験情報も入ってこなくて、劣等生のまま卒業ということになったのでした。
高校生の頃、どうすればよかったのか?

PRiMENON [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)]
以上、高校で授業がわからなくなり、成績が低下していった経緯をお伝えしました。
その後どうなったかというと、現役では大学受験をせず、そのまま浪人。というか、実質ほぼひきこもり状態へ移行しました。ここでも勉強はしていません。
しかし、高校卒業から1年たち、「このままではまずい」と思って、ようやく大学へ行こうと思えるようになりました。やっと危機感が芽生えてきたのです。というか、在学中は精神的に疲弊してましたので、そのくらいの回復期間は必要だったのだと思います。
で、そこから10ヶ月、ゼロから勉強して同志社大学に入学し、やっとまともな学生になることができました。
あとから考えると、4年間もわからなかったものが、たった10ヶ月で挽回でき、しかも同志社大学という割といい大学に合格することができたわけです。
では、振り返って、高校生の頃の自分はどうすべきだったのでしょう?
いま冷静に考えてみても、あのときあの状況で学業に真剣に取り組むことは不可能だったと思います。それはもう、やる気とか努力の問題ではありません。環境がわるすぎた。
——環境がわるい。
こう言うとすぐ、反射的に「環境のせいにするな」と説教をはじまる人がいますが、環境のよしあしというのは圧倒的に大きいのです。控えめに言っても、あの高校は自分には合わなかった。
もしあの当時に戻れるならば、遅くとも2年生のときに定時制か通信制へ転入します。これはもう、絶対に。親と担任が反対するなら、きわどい手を使ってでも、あの学校は脱出します。
あの頃は、定時制は働いている大人が夜間に行くものだと思っていたし、通信制高校のことは知りもしなかった。途中で移れるなんて思いもしなかった。知識不足から起こった悲劇です。取りうるはずの選択肢が、あらかじめ排除されていたのですから。
勉強法がどうとか、参考書をどれにするとか、どの予備校がいいとか、そんなのは二の次です。些細な問題です。決定的なのは、水の合わない学校へ無気力に通い続けること。
もし似たような状況の高校生がここを見ていましたら、1日もはやく、今の学校を抜け出し、近隣の定時制高校か通信制高校へ編入することをおすすめします。
高校教育はオワコンである
私が高校生だった2000年当時から、高校教育はオワコンになりつつありました。オワコン、つまり、時代に取り残された「終わったコンテンツ」です。
小中学校はまだ教育内容に実用性がありますが、しかし、高校でやる勉強は完全に受験という競争のための「競技」になってしまっている。そんなことに3年間も費やしていいのでしょうか?
中学までの基礎があれば、大学受験の勉強は1年で足ります。それを、普通の高校は3年間もかけるため効率がわるくなる。教室にも停滞ムード、無気力ムードが広がってくる。もはや、全日制の高校教育というものが限界に来ているのですよ。
できるなら、学校の勉強は最小限の労力で済ませ、10代のうちから自分の好きなこと、専門的な技能の習得に励んでもらいたい。そう思います。