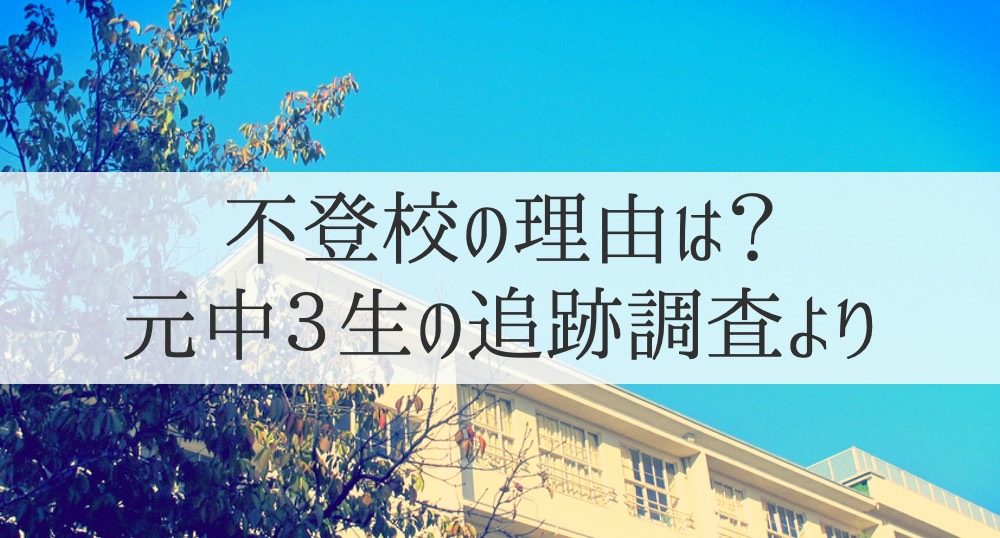このような疑問を抱えている親御さんが数多くいらっしゃいます。事実、不登校の児童生徒はここ26年で2倍にも増えています。
実は不登校の原因については文部科学省が行った詳しい追跡調査(統計)がありますので、この記事ではそちらを噛み砕いてお伝えします。さらに、元不登校の自分の立場から、望ましい対処法についても考えてみようと思います。
目次
不登校の原因の追跡調査を読み解く
なぜ子供が学校に行けなくなってしまうのか? 不登校のはっきりした原因がわからないために、悩むご家族も多いことでしょう。これについては信頼できるデータとして文部科学省の調査報告があります。
「不登校に関する実態調査」 ~平成18年度不登校生徒に関する追跡調査報告書~
これは平成18年(2006年)に中学3年生だった不登校(年間30日以上欠席)の生徒を対象に、3年後の平成24年(2012年)に追跡調査を行ったものです。つまり、中3で不登校だった生徒が18歳になった時点で自分の不登校についてどう捉えているのかというアンケート結果となっています。
この調査結果の中から重要な部分を取り出してご紹介していきましょう。
不登校のきっかけは「友人との関係」が最多
当時、中3で不登校だった子が18歳前後なってから回答した不登校のきっかけがこちらです(なお、複数回答ありのため合計は100%以上となっています)。
| 友人との関係 | 52.9% |
| 生活リズムの乱れ | 34.2% |
| 勉強が分からない | 31.2% |
| 先生との関係 | 26.2% |
| クラブや部活動の友人・先輩との関係 | 22.8% |
| 入学、転校、進級して学校や学級になじめなかった | 17.0% |
| インターネットやメール、ゲームなどの影響 | 15.3% |
| 病気 | 14.7% |
| 親との関係 | 14.2% |
| 学校のきまりなどの問題 | 10.0% |
| 家族との不和 | 10.0% |
| 家族の生活環境の急激な変化 | 9.7% |
| とくに思いあたることはない | 5.5% |
| その他 | 16.0% |
このように、友人関係が不登校のきっかけとの回答が突出して多くなっています。ここにはいじめやからかわれた経験なども含まれます。他にも先生やクラブの先輩などとの関係がきっかけとする答えが多く、やはり学校という空間での人間関係が不登校の最大の原因となっていることがわかりますね。
一方、勉強が分からないのがきっかけで学校に行けなくなったと考えている者も3割を超えており、決して少ない数字ではありません。
この調査は中学3年生だった不登校の生徒を対象としているため偏りはありますが、きっかけをまとめるとこのように言っていいでしょう。
不登校の原因の半分以上は学校での人間関係によるもの。その他、勉強に付いていけないという理由が3割、病気や家庭環境といった理由がそれぞれ1割強。
不登校になった時期は中1中2が断トツ
同じ調査のなかで、学校を休み始めた時期についても報告されています。こちらも不登校の原因についてヒントを与えてくれそうです。
| 小学校1年生 | 4.2% |
| 小学校2年生 | 3.0% |
| 小学校3年生 | 4.8% |
| 小学校4年生 | 6.0% |
| 小学校5年生 | 7.6% |
| 小学校6年生 | 6.1% |
| 中学校1年生 | 29.1% |
| 中学校2年生 | 25.8% |
| 中学校3年生 | 10.1% |
| わからない | 3.5% |
見てわかるように、不登校の始まりとしては中1がもっとも多くなっています。「中1ギャップ」という言葉もありますが、やはり小学校から中学校へ上がるときに人間関係も勉学の内容も激変するためでしょう。
思春期に差し掛かり、勉強の内容もより抽象的かつ受験を意識したものに変わっていく中学生というのは不登校が増えるタイミングだと考えられます。
季節的には、1年を4つに区分したうち「7月〜9月」にもっとも休み始める人が多いという結果になっています。ここには夏休み明けが含まれるため、やはりその時期に不登校となる子供が多いのでしょう。この時期には子供の自殺も増加するため、とりわけ注意が必要です。
不登校継続の理由は「無気力でなんとなく」
先ほどは学校を休み始めたきっかけについてご紹介しました。今度は不登校の「継続」の理由を見てみましょう。こちらは先ほどとは選択肢が変わっています。
| 無気力でなんとなく学校へ行かなかったため | 44.4% |
| いやがらせやいじめをする生徒の存在や、友人との人間関係のため | 41.4% |
| 学校へ行こうという気持ちはあるが、身体の調子が悪いと感じたり、 ぼんやりとした不安があったりしたため | 43.7% |
| 朝起きられないなど生活リズムが乱れていたため | 34.1% |
| 勉強についていけなかったため | 27.4% |
| 学校へ行かないことをあまり悪く思わなかったため | 25.6% |
| なぜ学校に行かなくてはならないのかが理解できず、自分の好きな方向を選んだため | 19.9% |
| 先生との関係(先生がおこる、注意がうるさい、体罰など)のため | 16.6% |
| だれかが迎えに来たり強く催促されたりすると学校へ行くが、長続きしなかったため | 12.8% |
| 遊ぶためや非行グループにはいっていたため | 9.1% |
| 保護者やまわりの人に学校を休んでもいいと助言されたため | 8.5% |
| 親から登校するようすすめられず、家にいても親から注意されなかったため | 6.6% |
| 学校から登校するように働きかけがなかったため | 4.7% |
| その他 | 14.3% |
| わからない | 3.0% |
やはり人間関係にまつわる問題があるために不登校を継続するという人は多くなっています。
しかし、きっかけの部分との違いで言うと「無気力でなんとなく」や「ぼんやりした不安」といった漠然とした理由がそれぞれ4割を超え、大きな理由となっています。これは、しばらく不登校を続けたためにいじめや仲間はずれのリスクは減少したものの、そのまま再登校するきっかけを掴めずにいる状態ということかもしれません。
また、生活リズムの乱れも34%の方が理由としています。私自身も高校時代の不登校で経験がありますが、一度夜型の生活リズムにはまってしまうと朝起きるのが難しく、学校へ行けない日が続いてしまうものです。
27.4%となっている「勉強についていけなかった」という理由も見逃せません。学校の授業はおおむね積み上げ型ですから、1,2週間も休めばかなりの遅れを取ってしまうことになります。
不登校の理由は人間関係・生活リズムの乱れ・勉強
以上の結果をまとめてみます。
不登校の原因は半分以上が人間関係によるもの。また、生活リズムの乱れと勉強についていけないことも3割程度で理由となっている。
不登校の生徒の支援ニーズは心のケア
さて、では不登校をしていた生徒は、中学3年生当時どのような支援を求めていたのでしょうか。これについても同じ調査の中にアンケート結果があるので見てみましょう。
| 心の悩みについての相談 | 32.0% |
| 自分の気持ちをはっきり表現し たり、人とうまくつきあったりするための方法についての指導 | 30.7% |
| 学校の勉強についての相談や手助け | 24.5% |
| 友人と知り合えたり、仲間と過ごせたりする居場所 | 24.4% |
| 進学するための相談や手助け | 22.3% |
| 将来生きていくためや仕事に役立つ技術や技能の習得についての相談や手助け | 21.1% |
| 仕事につくための相談や手助け | 11.3% |
| 規則正しい生活習慣についての指導 | 8.9% |
| その他 | 5.1% |
| とくにない | 31.9% |
心の悩みや人間関係に関する支援が必要であった。やはり、このような支援があればよかったと考える人が3割以上と多くなっています。不登校のきっかけも継続理由も学校での人間関係にまつわるものが最多でしたので、これは頷ける結果ですね。
テレビの特集やインターネットの記事を見ていますと、そこには何らかの支援を受けることのできた子供たちがよく登場しています。大人の用意した支援の仕組みに繋がれたこそ、彼らは可視化され、その声を聞くこともできているのです。
しかしながら、多くの不登校の生徒はそのような支援を受けられていないのが現実のようです。システムとしては適応指導教室やフリースクールがあり、保健室登校のような措置もありうるわけですが、多くの不登校児童・生徒たちはただ学校を休んでいるだけで、適切な対処を受けられていないのかもしれません。
不登校には早めに別の選択肢を

わが子が不登校となったとき、まずは元通りに登校させようと努力する。これは理解できます。起きてこない子供の布団をひきはがし、無理にでも登校させようとする。これで一時的には学校へ行かせることができるかもしれません。
しかし、上で見たように、不登校の理由は学校での人間関係や無気力感にあります。物理的に学校へと送り出したところで、こうした問題は何ひとつ解決しません。むしろ、本当の問題を放置したまま登校を強いれば、さらに問題をこじらせてしまうおそれもあります。
私自身は高校時代に不登校を経験し、それでもだましだまし登校を続けて卒業にたどりつきました。結果、浪人はしたものの二十歳で大学へと入学し、見かけ上は「普通の大学生」となりました。が、不登校時代の心の傷は三十代となった今も完全には癒えていません。よくあの頃の夢を見ます。今でも当時の絶望感・孤立感は尾を引いており、フリースクールや通信制高校への転入、あるいは高認を経ての大学受験など、もっと適切な支援を受けたかったと思っています。
わが子の不登校という問題に直面したとき、当座は「何とかまた学校へ」と考えてしまうことでしょう。これは仕方ありません。しかし、その状態が数週間、数ヶ月と長引くようでしたら、いつまでも再登校ばかりをゴールとする発想は切り替えた方がいいと思います。
現代においては居心地のわるい、自分の適していないコミュニティに無理をしてまで適応する必要はありません。
再登校より大切なこと
不登校のきっかけや継続理由は人間関係によるものが大半で、その他には勉強の遅れ、生活リズムの乱れなどがありました。
しかし、これらはあくまでアンケート結果に過ぎません。ここには現れない社会的な要因として、そもそも学校制度が今の時代にそぐわないということが指摘できるでしょう。つまり、時代は変わっているのに、学校が旧態依然とした教育を続けているために、その歪みが児童生徒の不登校というかたちになって現れているのです。私は、これは子供たちによる「無意識のデモ活動」と言ってもいいと思います。
こうした事態に直面したとき、子供を無理に学校へ行かせる必要はありません。必要なのは、できる範囲でその子の存在を承認し、よりそい、適切な支援へとつなげることです。
では、子供が不登校となったとき、再び同じように登校させる以外にどんな選択肢があるのか? どういった組織・機関を利用すればいいのか? これについてはまた別の記事でお伝えします。